今回は円滑なボーカルレコーディングの進め方ついてMix師の観点から解説していきたいと思います。
ボーカルの方は、声帯と言う楽器を使い、言葉をメロディーにのせて音楽を表現しています。
他の楽器を演奏する方とは違い、人間の筋肉を使用しているため演奏可能な時間は他の楽器に比べてとても短いです。
皆さんもカラオケなどにいかれて、2時間程度過ごすと帰る頃には声がガラガラになっている経験があると思います。
どんなにうまいボーカリストでも、レコーディングやライブの後には声帯を消耗する状態になります。

また声が起きてくる時間帯は、その人の毎日の生活リズムに大きく影響しているため本人が朝起きてから通常の声になるまでの時間が必要になります。
毎日の体調の変化もあるので、1ヵ月のうちのどのあたりでボーカル録音をするかなども考慮が必要です。
これらのことを考えると、ボーカルを録音すると決めた日の中でパフォーマンスを発揮できる時間帯は大変短く、その機会を逃すとまた別の日に録音しなおしになってしまうことも少なくありません。
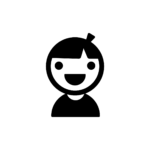
昨日はボーカル録音でした
新しい機材の準備に戸惑ってしまい、ボーカル君を待たせてしまったんだ
1時間遅れで録音を開始したのだけど、1サビの感じが気に入らないので40回も同じ箇所を録音したんだよ
6時間くらい録音を続けたけど、後で全体を聞いてみたら後半にいくにつれて声がガラガラになっていてまた今日も録音をし直すことにしたんだ
ちゃんと練習してきて欲しいなぁ
こんな内容でずっと悩んでいませんでしょうか?
初めて一緒にレコーディングをお手伝いさせていただく現場で、違和感を覚えるのはボーカルレコーディングやドラムレコーディングの方法やスケジュール管理です。
音楽の作り方が自由なように、録音の仕方も、スケジュールの管理方法もこれが正解で他が間違いというような絶対的なルールはないと思います。
楽器を演奏していて、メンテナンス不足で音が出なくなっても別の楽器に交換することでまたレコーディングを進めることが出来ます。
しかしボーカルの声帯やドラマーの身体は1つしかありません。
音楽という要素とスポーツという要素が複合しているという認識を持っている方は残念ながら少ないと思います。

それでは詳しい内容に入っていきましょう!
ガイドメロディーに使用する音源に注意する(作曲をする場合)
ボーカルレコーディングの記事ですが、まずは作曲段階の事について解説したいと思います。
作曲する際にメロディーラインをボーカルに伝えるために、声ではなく他の楽器で伝えることが多いと思います。
MIDI情報も同時に渡せるので、メロディーラインの間違った伝わり方などがないため便利な方法だとは思います。

- ここで2つの問題点が生まれていると僕は感じます。
- ボーカルの表現要素をMIDI情報に落とし込むのはかなり難しい
- ピアノなどの音源を使用している場合は、メロディーがどこで切れているのかわかりにくい
ボーカルは微妙な変化を繰り返しながら、言葉をメロディーにのせて表現していきます。
演奏する前に楽器をチューニングをしようこちらの記事の中でも解説しているような、楽器の音階の中を、様々なピッチで表現していきます。
MIDI情報で伝えられることは、わずかな情報でしかないため、ガイド音として考える必要があります。
- 大抵の方がピアノでメロディーを打ち込んでいると思いますが、これも誤解を生むポイントだと思います。
- ピアノは音が発音された後、常に信号が小さくなっていく楽器です
- ボーカルは音が発音された後、任意のポイントから信号を大きくすることができます
2つの音源の違いわかりますでしょうか?
細かい違いですが、この違いが後々、大きなニュアンス違いを生んでいく原因になってきます。
またピアノはペダルを使用することによって音を停止する事が出来ますが、その機能を使用してる方がほとんどいないので、音が発音する場所、どのピッチで鳴らすかしか、ボーカルに伝えられない状態になっていることが多いです。
これらのことを考えますと、優しい音色のリードシンセか、サックスなどの楽器でメロを入力すると良いと思います。

ちょっとスーパーのBGMっぽいですけど、気にせずいきましょう!
メロディーラインを考える(作曲をする場合)
まずこれから作る曲を歌う方達が、何人ボーカルのいるグループなのかを考えます。

複数ボーカルがいるグループであればある程度問題ありませんが、ボーカルが1人しかいない場合、メロディーの合間で息を吸うタイミングを作らなければいけません。
レコーディングであれば、いくつもトラックを重ねることは可能ですが、実際に演奏する際にはどのパートを歌うのか選択する必要があります。

歌と他の楽器の切り替わりなどで印象の変化も効果的になります。
その他の楽器の見せ場を作ることにも使用できるので、息継ぎとのバランスも考えて調整しましょう。
ハモやコーラスのメロディーライン作成(作曲をする場合)
メインボーカルのパートが完成したら、コーラス関係のラインを作成します。
まれに、レコーディングをしながら考えだす方もいますが、声がベストな状態はとても少ない貴重な時間です。
事前に準備をしておきましょう。
完成したら、通して聞いてみて、コーラスの入れすぎになっていないか考えます。
コーラスを入れている場所は、楽曲のアクセントになります。

コーラスは例えるなら、白米に対する納豆や、梅干し、海苔ぐらいのパンチ力があります。
白米とセットになった時に、それぞれのよさが引き立つので入れすぎや伴奏との絡みがとても重要になってきます。
実際に自分で歌ってみる(作曲をする場合)
細かいスタッカートのニュアンスや、音と音の繋げ方などは実際に歌ったほうが、伝わりやすいです。
息継ぎが苦しい部分なども確認できるので、この作業はとても重要になってきます。
- 歌詞がない場合は、
- 「ラララ」など1つの言葉で歌う方法
- 適当な言葉で歌う方法
などがあります。
ボーカルの方の好きな方で良いと思います。
適度な言葉で歌ってしまうと、ボーカルの方が歌詞を書く場合に言葉のイメージに引っ張られてしまう場合もあるので、本人に確認をしてみましょう。

ボーカルに仮歌を歌ってもらう
仮歌を歌うことは、その楽曲が自分に合っているかどうかを確認する重要な工程です。
作曲をする方と歌う方の間でよくおこる問題がこの工程をはぶいたためにおこってきます。
ボーカルの声帯はそれぞれ違う楽器であり、一番高い音、一番低い音、裏声に切り替わりやすい音の繋がりなど、皆さんバラバラです。
ギターやベースは、ダウンチューニングなどを使用して別の音階を演奏することができますが、ボーカルの声帯は変更することはできません。
「歌ってみた」であれば、音階の変更が必要かの確認をするべきですし、作曲をする場合も事前に既存の曲をいくつか歌ってもらっておくと良いと思います。
ボーカルの方が好きな曲のメロディの形や、実際のデータから高い音符の時の声のかすれ感なども確認できると思います。

想像しておくことは、最終的に作曲した曲を2時間くらい歌い続ける日がくるという事。
レコーディングの日だけ歌えるだけの曲を作っても、お客さんはライブでパーフェクトにそのメロディーを歌うボーカルの姿をみたいです。
ボーカルの声帯と合わない曲を作るのは意味のない事ですし、そのグループのやるべきことではないと思います。

オリジナル楽曲を作るということは、そのメンバーで表現することです!
ボーカルレコーディングの日を決める
ライブなどの日程と離れた日程が望ましいと思います。
スケジュールが過密な方でも、最低1日はあけた状態でレコーディングの日程を決定します。
男性の方であれば、あとは体調の問題を気にするくらいです。
女性の場合は、1ヶ月の周期も気分に大きく影響があるので、万全の日程でレコーディングをする方が僕は良いと思います。
歌を録音する日程は、最低でも1日は開けた状態でスケジュールを組むようにします。
またアルバムなどの大規模なレコーディングであれば、予備の日程を準備しておくようにしましょう。
体調の変化は必ずおこるものです。

録音を開始する時間も重要です。
ボーカルの方は、自分が毎日何時に起き、どの時間帯が声が一番本調子になる時間帯になるかの確認をしましょう。
前日に遅くまで起きていたりすると、本調子になるまでの時間に変化があると思います。
レコーディングの日程までの期間は、同じような生活を行い体調を整えていくと良いと思います。
歌い始める時間は、このため歌い始める時間帯が他の楽器より少し遅いことが多いです。
レコーディングに新しい機材を使用したい場合
可能であれば仮歌の際に試してください。
本番で何か試すという行為自体が危険なことです。
どうしても本番の日に試したい場合は、記者会見の時のように複数のマイクをボーカルの前に並べて、一回で全ての機材を確認する方法があります。
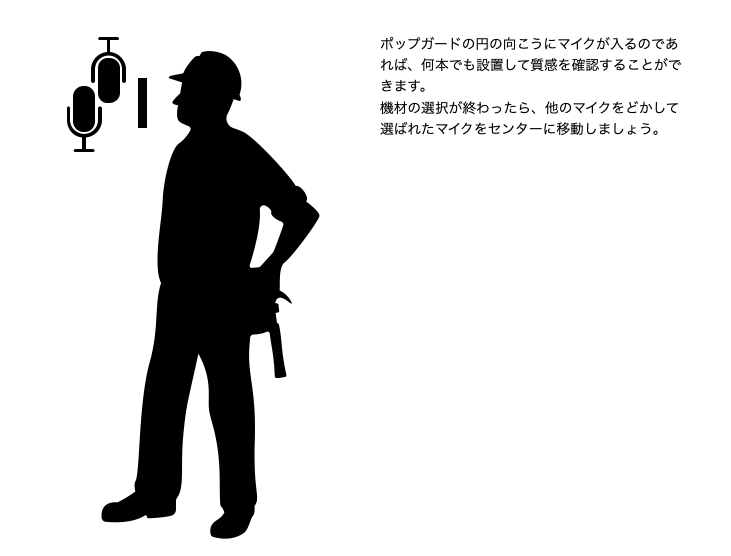
新しい機材といつもの機材を使って同時に録音します。
その中で気に入った物を選択するという感じです。
機材選びは、スムーズにボーカルの貴重な時間をロスしないことが前提です。
いつもの場所ではない場合は、いつもの何かを用意する
ボーカルの方は、いつも自分が歌っている場所ではない場所で歌う場合、いつもの場所にある何かを持っていくのは、気分的にも良いと思います。
飲み物であったり、歌詞を挟むバインダーであったり、目に見える風景の写真であったり、おまじないのようなことかと思いますが、ブースの中でどこかのパートにつまずいた時に安心できる何かはあった方が良いと思います。

レコーディングでは、うまく歌えない箇所に差し掛かった時、トークバックから聞こえてくるプロデューサーや、作曲者の言葉が冷たく聞こえてきてしまうものです。
レコーディングエンジニアは、この時2つの空間の共通点を技術的に探し続ける職業でもあり、円滑なコミュニケーションを配慮していく役割もになっていると思います。
録音の進め方、チャンスはファーストテイク
ここまで準備を進めてきますと、ボーカルの方がどのようにその楽曲に向き合ってきたかが重要になり、レコーディングの当日は一定の答えしか出せないと僕は思います。

レコーディングエンジニアはMix師がMixの前に行う大切な行動こちらの記事で解説したような行動をとったら後は以下の内容に注意していきます。
- 録音時に気にしていること
- 事故なくDAWにおさめること
- 入力レベルを想像して、事前に設定し、ファーストテイクで微調整
- ボーカルが夢中になって、マイクとの距離が適切な位置からズレていないか
- HAやコンプレッサーなどの機材が適正な値で稼働しているか
貴重なファーストテイクも使用できるように、素早い設定が求められます。
機材の機能などはあらかじめ理解しておき、皆さんが安心してレコーディングをおこなえるように気を配っていきましょう。
全体を通してクオリティーを考える
- ボーカル録音の方法は色々あります。
- ファーストテイクのみの方
- 5テイクくらい録音する方
- 録音が止まったところから、録音を続けていく方
- セクションを分けて録音していく方
方法は色々ですが、僕は5テイクくらい録音する方をオススメします。

楽曲は、時間の流れがとても重要で、1番を歌った後に、2番がきます。
リスナーは必ずその順番で楽曲を聞いていくものです。
1番で感じた印象を持ったまま、2番の言葉と読み取っていきます。
時間の流れを無視した録音方法では、同じ言葉の繰り返しとなってしまいリスナーの感情移入も難しいと考えます。
ボーカル録音に慣れたチームであれば、5テイク録音した後に10分程度の時間でそれぞれのテイクの良いと思うパーツをつなぎ合わせて確認をすることが可能です。
その後どうしても気になる部分があれば、その箇所だけ録音をし直してみる。
しかし、大抵の場合ファーストテイクに気持ちが勝てないことが多いと思います。
何回も挑戦しても乗り越えられない箇所があるのであれば、それは録音の前の準備段階で失敗しているということかと思います。

当日ではどうにもならないことをレコーディングの日におこなうのは、貴重な声の時間を失うことになるので、全体のクオリティーを考えて次に進みましょう。
本番で練習以上のことは出来ない
「本番では70%の力しか発揮出来ない」などの言葉をよくみますが、どんな事柄でも同じようなことが言われていると思います。
高級な機材のある高級なスタジオの中に入ると、少し強くなった気もしますが、基本宅録と変わりはないと思います。
声を張り上げること、モニターのしやすさが向上しても、その楽曲の言葉の配置とどのくらい向き合ったかだけが重要なポイントになると思います。
日頃、ハンドマイクのみで練習している方は、スタンドマイクも練習しておくと良いと思います。
レコーディングで使用する多くのマイクは、スタンドに固定されているマイクです。
手に持って歌う体制と、固定されているマイクに対して歌う体制は違うので、違和感があると思います。

ハモ、コーラスは別の日でも問題ない
コーラス関係は、マイクや機材の設定を変えることが多いので、同じ日に録音が出来なくでも問題ありません。
コーラス関係を宅録で入れることも最近は多くなってきました。
貴重な時間とお金は計画的に使っていきましょう。

使用したマイク、機材の設定は、写真などに残しておく
録音をした、3日後にやっぱり歌詞を変更したいなどの連絡があることは良くあることです。
使用した機材は、必ず設定を記録しておきましょう。

その点、Mix用とRec用オーディオインターフェイスを分けて考えるで紹介したUniversal Audio Apollo / Twin X or Apollo x4などの機材は大変便利ですね。
まとめ
- 長くレコーディングに立ち会っていて感じることの1つに、ドラム、ボーカルのスポーツ要素の大きさの理解度の低さがあります。
- BPM180以上の楽曲を、2時間のライブの中で何曲も叩くドラマー
- シャウトとハイトーンと早口言葉を繰り返すアレンジの楽曲を、2時間のライブの中で歌い続けるボーカリスト
陸上競技のような過酷な世界観で身体にダメージを与えながら表現していることを、あまり気づかれていないのではと心配になります。

もちろん、他の楽器でも体力を消耗することは間違いありませんが、引退や脱退などの多くはこの要因が大きく影響していると感じます。
色々な音楽のジャンルがありますが、自分が表現したいことと活動に使える時間、体力の関係を総合的に判断しながら音楽を考えると、より後悔のない音楽ライフを楽しめるのではと思い記事に書かせていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!






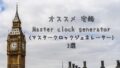

コメント