僕がNATIVE INSTRUMENTS KOMPLETEと同じ位大好きな ソフトシンセサイザーをご紹介します。
シンセサイザー入門者にはNATIVE INSTRUMENTSのプラグインパックをオススメしていますが、 最近の音楽の傾向によったプリセットが多く入っているので、 一定のジャンルには向かないシンセサイザーである事は確かです。
懐かしい音楽の音が好きな方には、ARTURIA V COLLECTIONの方が安心して音作りを進めていくことが出来ると思います。
シンセサイザーを使い初めた最初の頃はプリセットを使用して楽曲に音源を当てはめていくことも良いとは思いますが、 オリジナル楽曲を作る意味ではより独創性のある楽器を使用していくことが必要になってきます。
ソフトシンセを購入してプリセットを選択していくだけでは、どうしても他の人と同じような楽曲になってしまい、リスナーにどこかで聞いたことのある曲という印象を受けてしまうことは避けられないでしょう。
またARTURIA V COLLECTIONは実際に存在していたシンセサイザーをパソコンの中で再現することに集中しているソフトシンセなので、 当時実機を使っていた方もすぐに使用することが可能です。
アレンジャーの仕事をしている方でこのシンセサイザーパックのみですべての仕事が完了できるとは思っていませんが、NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETEを購入した次に購入して欲しいシンセサイザーパックです。
この2つを所有していれば、たいていの仕事は無事終わらせることができると思います。
深夜に特殊な音源を求めて友人に電話をするような機会も最近は大変少なくなってきましたね。

それでは詳しい内容に入っていきましょう!
ARTURIAの方向性
MINI V を代表とする有名ないくつかのシンセサイザーパックとして発売が開始されました。
その後ありとあらゆる有名な実機を安価な価格帯でパソコンの中に再現していきながら、MIDIコントローラーやハードウェアシンセ、プラグイン、オーディオインターフェイスなども 開発していきます。
エミュレーションのソフトシンセ関係で文句を言う方をまず見たことがありません。

予算的に実機を購入できない方であればほとんどの方がこちらのソフトシンセを購入していると思います。
種類もどんどん増えてきていますので、サンプラー系の音源以外はNATIVE INSTRUMENTS KOMPLETEよりも人気になっていると思います。
MIDIコントローラーや、オーディオインターフェイスなどは使用している方をほとんど見る事はありませんし、僕も誰かにオススメすることはないです。
ハードシンセは、MiniBruteが発売されたときに かなり話題になりましたが現在ではそれも落ち着いてきているとは思います。
決して悪い物ではないとは思いますが、エミュレーションのソフトシンセ関係が本当に良く出来ているのでライブで演奏する方以外は、迷わずソフトシンセを立ち上げてしまうと思います。
そこまで軽いソフトではないのでパソコンのスペックは充分注意して購入をした方が良いと思います。

また画面サイズが小さい環境の方も注意が必要です。
それなりに大きい画面サイズもしくはサブディスプレイがあった方が作業し易いと思います。
ARTURIA V COLLECTION 9
シンセサイザーの名機が大集合
Arturia / V Collection 9
数々のヒット作品を支えてきたシンセが大集合
メンテナンスされていない実機よりも使用しやすい
サンプラー機能機能以外は大変充実している

音質
操作スピード
マニアック度
痒いところに手が届く
発売された当初は内包しているシンセ数が少なかったですが、現在ではとてつもない数のシンセサイザーのパックになっています。
| マルチ音源 | Analog Synths | Digital Synths | Keyboards & Organs | Acoustic & Electric Pianos | Augmented Acoustic Instruments |
| ANALOG LAB V | KORG MS-20 V | SQ-80 V | FARFISA V | PIANO V 3 | AUGMENTED STRINGS |
| CS-80 V 4 | PROPHET-VS V | MELLOTRON V | SOLINA V | AUGMENTED VOICES | |
| PROPHET-5 V | MATRIX-12 V | B-3 V | CLAVINET V | ||
| VOCODER V | CMI V | STAGE-73 V | |||
| OP-XA V | DX7 V | WURLI V | |||
| JUN-6 V | SYNCLAVIER V | VOX CONTINENTAL V | |||
| BUCHLA EASEL V | CZ V | ||||
| MINI V | |||||
| SEM V | |||||
| JUP-8 V | |||||
| ARP2600 V | |||||
| MODULAR V | |||||
| SYNTHI V | |||||
| EMULATOR II V |
気になる点としては、リズム系とサンプラー系が現在弱いことです。
以前はSparkというリズムボックスが 内包されていましたが現在はセットになっていません。
この辺りはその他のシンセを使用するしかなさそうです。
ワンショット系のサンプラーならBATTERY 4
オールマイティなサンプラーならKONTAKT 6
あたりがオススメです。
waldorf / PPG Wave 3.VとAKAI Professional / MPC4000あたりを再現するのが良いと思いますが、足りない物はハードウェアで準備すると作曲の空気感も変化があって楽しいです。
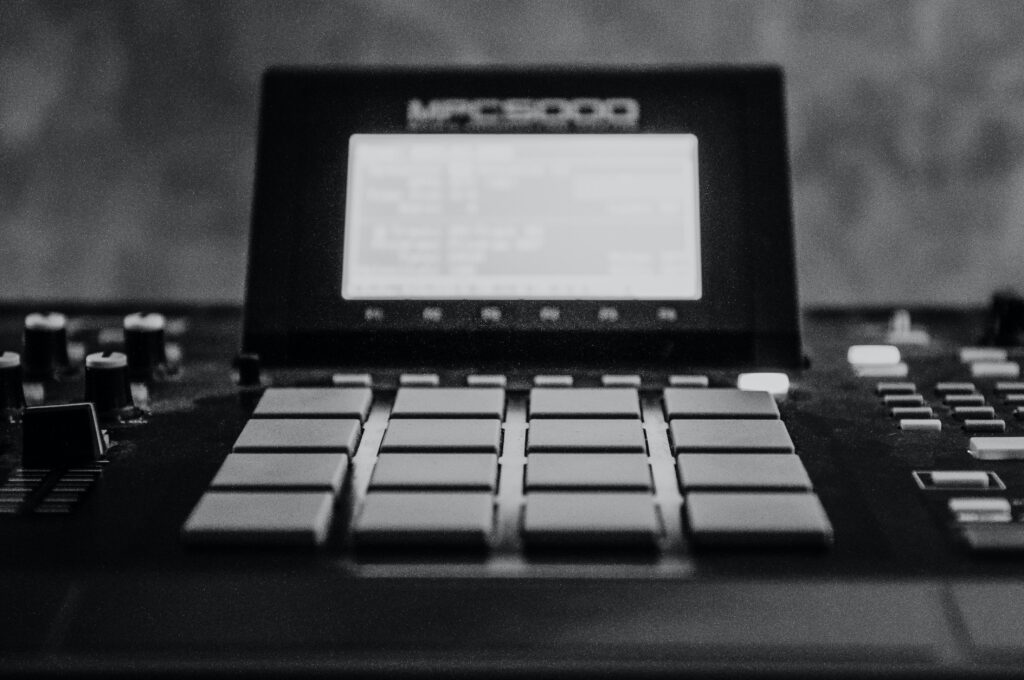
DrumBruteという製品がもう少し、色々なリズム音源などに匹敵する機能が増えていったら良いなとも思いますが、僕はELEKTRONが好きなので、サンプラーはハードウェアで良いかなとも思います。

リズムはやっぱり、叩いて入力する方が良いと思っています!
ソフトシンセサイザーを使用する時に是非試して欲しいこと
アナログ領域で音を処理する
それでも実機との違いを感じる方は多くいると思いますが、 ソフトシンセを使用する際にぜひ試してもらいたいことがあります。
一度パソコンからオーディオ信号を出してまた好きな機材で録音してみること。
DAWだけで作業してきた方からしたら、特に意味が無いように感じると思いますが一度やってみるとアナログ領域で起こる変化はとても面白いです。

高級な機材を準備するという話ではなく、リアンプ・ボックスなどを利用していかに独特な音像を作り上げるかということをやってみてもいいと思います。
僕はお気に入りの回路を3種類程度準備したらどんなデジタル機器も効果的に音像の加工ができると思っています。
テープ処理だったり、コンプレッサーだったり、真空管だったり気に入った回路を少しづつ集めていくと良いと思います。
宅録ではランチボックスのような省スペース機材がちょうど良いと思います。
アナログ領域はある程度の予算をかけないと逆に音がすぐに劣化していくジャンルでもありますので、少しお金を貯めてから少しづつ導入していくと良いと思います。
スクロールが出来るマウスや、つまみをコントール出来る入力デバイスを用意する
シンセサイザーは音色を作るとき、つまみを回している感覚がとても重要です。
MIDIキーボードについている物でも、なんでも良いので準備しておくと良いと思います。

DAWによっては、マウスオーバーしている時にスクロールホイールが該当のつまみに対応する機能がついている物もあります。
たくさん摘みがあっても同時に2つしかコントロールはしないと思うのである物で設定してみてください。
この2つの準備をしておけば、実機とそこまで変わらないと思います。
まとめ
今回はARTURIA V COLLECTION 9について解説いたしました。

たくさんのソフトシンセサイザーが毎月発売されていっていますが、ほとんどの商品がこれらの王道のシンセサイザーで出せる音ばかりです。
プリセットを選択するだけの音作りに飽きてきたら、是非1から音を作る楽しみを味わって欲しいと思っています。
少しリズム関係やサンプラー関係が弱い印象がありますが、NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETEを購入した後に是非購入して欲しいシンセサイザーです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!





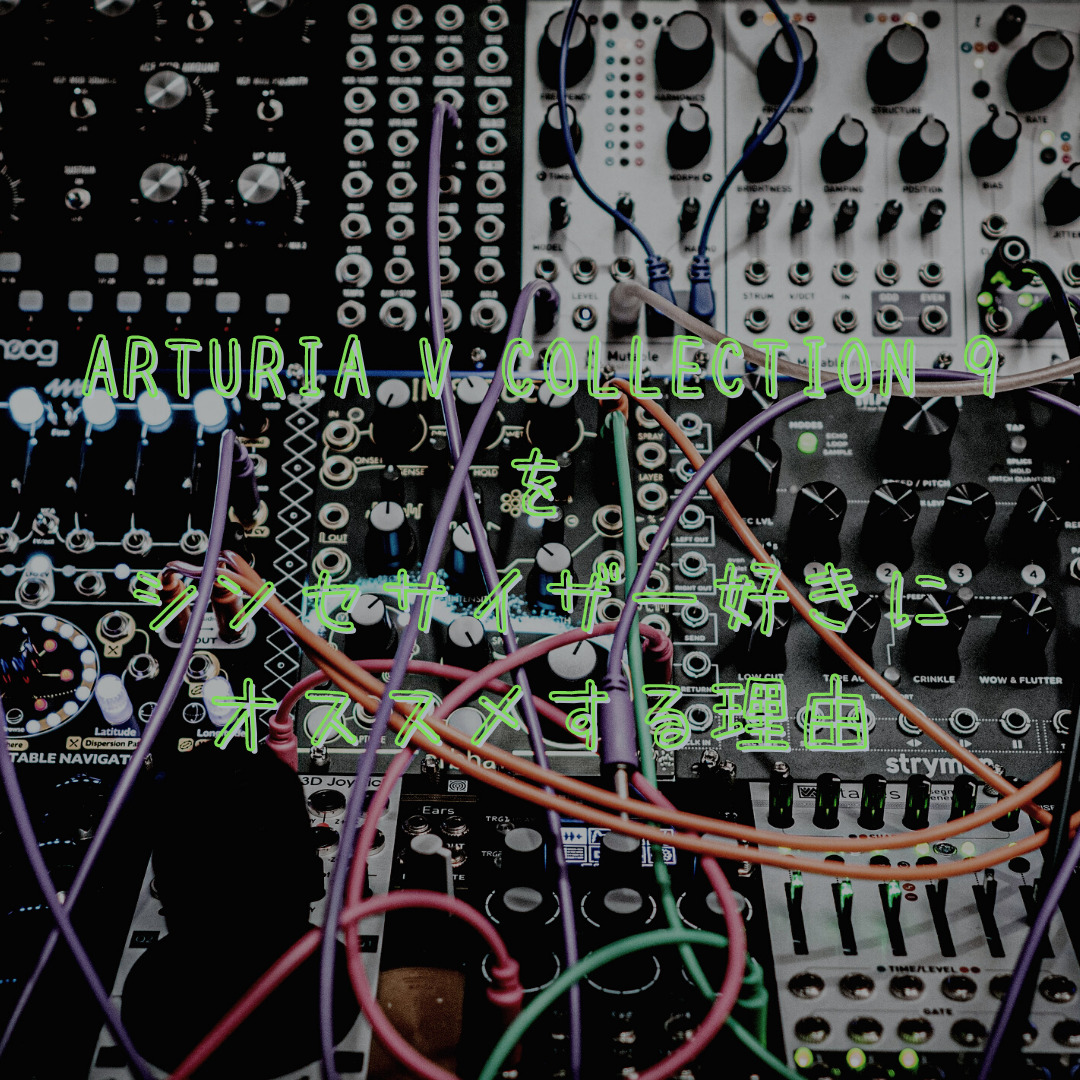





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d22629e.0ecf0a7d.1d22629f.2ae4246c/?me_id=1303873&item_id=10008394&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frockonline%2Fcabinet%2Fproduct%2F05144144%2F05144145%2Fvcollection9_license.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


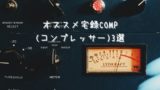



コメント